逃げ・・の捉え方が根本から変わる『羊飼いの柵(門下生)』のスケープゴートの意味で『追放される山羊側(門外漢)』の忌で、根本から束縛からの解放を理解するお話。裏カタカムナ『に』の独自解釈
逃げとは
危険を避けて、相手の力の及ばない所へ去る、また身を隠す
避けて、不利な情況におちいらないようにする
逃げ・・というと無意識的にそれは『良くない事』だと教えられてきたが・・
今の私はこう解釈する
『兆しへ進む』
逃げとは、基本的にその場に『停滞』してはいないで『動き出すエネルギーを発振』している振動エネルギー
にげの言霊は
①圧力を内に放出
②圧力を反対に放出
①の場合は動機となるエネルギーが生まれている
②の場合は距離を取っている
それは『何』に対してか?と書けば
何=『人の可(能性)』
『対象となる物事』から『逃げ』というのは、何らかの『動機が内側』に生まれ、そして『対象から離れよう』としている
では、その動機のエネルギー『どこ』へ向かうか?
それが『兆しへすすむ』と書いて『逃』となる
逃げ・・という『動機』が生まれるという事は『合わない』という事
『郷に入っては郷に従え』の中では・・『郷の業を修める修業』の真っ只中の『門下生としては裏切り』であるが
『裏切り=背信行為』とは、『北の月の人が言う行いの為』となり、基本的には『争いを好まない方向へと救いを求める事』とも言える
逃げの先は『心の安心や安全』である
それは『心が壊れないように護る』ための『精神の導き』でもある
『魂の年齢』や『求める業=回収』が必要な『段階(密度)』は人によって違う
ちょっとやってみたら、もう『足るを知って満足している』・・にも関わらず
いつまでも『同調圧力の惰性』で『終わった事をだらだらと繰り返している』のが『性に合わない人(頭角を現す)』にとって『その環境』にいても『生が無い』
だから、新たな兆しへすすむ=逃
人は『死ぬ時』も『死に場所』も選べないから、何処で『野垂れ死に』しても『迷惑』が掛かる『飛ぶ鳥跡を濁す』
だから自分的には『心のままに前向きに兆しへ進んだ』としても、残された者には、『面倒を遺していく裏切者の逃げ=罪』をつけられる
これが『スケープゴートシステム』
『追放した山羊』に『全ての羊の罪』をなすりける=『悪者』にする
だからだろうな・・
魂の年齢が『老年期』になると、『自然に独学』で学びたい事を学び、『組織に属さない』ようになる。組織に属するとどこにいっても『郷の業という柵(しがらみ)』があるから
空の星ひとつ見上げて『自由に観測』しても「それは天文学的には・・」という『門下生の常識』に合わせたら・・『その界隈の常識で答え合わせ』して『間違いを指摘』してくる
そもそも『間』が違う
そっちは柵(さく)の中の『不自由な羊』であり
こっちは柵の外に出た『自由な山羊』
そっちから見れば『逃げ』という『罪で束縛』しようとしても
迷える子羊ではなく『頭角を現した山羊』からすると『兆し』へ進んだ=逃
このように、『常識という界隈の物事の捉え方』の多くは、『柵の外に逃げ』をしないように『策』を練った『罪の植え付け』による『レッテル封じ』
だから、『禁忌』は面白いんだよ?
レッテルを貼られた物事を『覆して』いけばいい
都合で貼られた『お札』をはがし、そこに『封印』された物事が『何』だったのか?
何=『人の可能性』
それは常識の中の『策の柵(しがらみ)の門下生』では気づかない
だから『門外漢』として門の外に広がる『自然な漢字の表現』に魅了されていく
『逃げ恥』というのも面白い言葉
『兆しへ進み心に耳を傾けろ』という事でもある
そりゃ逃げるは恥だが『生活の役に立つ』はな
あくまでも、『惡魔(一+一を支える心)』でも、『亜空間(有るけど気づかない)』でも
これは一般常識的な『意味』ではなく、『己の心=忌』で捉えた『観点』である
柵(しがらみ)の外の自由な門外漢=『門外の漢字』の捉え方
だけど、『解放的』だろ?何にも『束縛』されず
自由に『兆しのほうへ進む』のだから
そのためには『郷(門下)』に入らず『門前の小僧』として『門の前の人』として心で『聞き耳』たててればいい
「恥知らずがなんか言ってらww」と門+人で『閃』
『柵の中の策(レッテル)』が聞こえたら『門の外で漢字』にしてレッテルの策を広める
そうすれば、柵の策にはまる『無知蒙昧な人(知識格差)』はいなくなる
みんな『知恵者』になれば、誰も思い込みで『騙されない』
『学問』で『識字率、読解力を磨く』というより
『心』が『感じたまま』に素直に『悳』を積む
合うか?合わないか?
合わなければ逃げでいい
三十六計逃げるに如かず
形勢が不利になった時に、あれこれ策を講じるよりも、逃げるのが一番良い
ハハハ、これもこうやってみる
『三+六』は『計』なんぼ?=『九』
一切皆苦は一切皆九
『苦』を対象に『兆しへ進む』=苦から『楽』へ『位置』を変える
それが『安心・安全の兆しへ進む』って事でしょ
難しい事も『有難い事』だけど(門下生)
『楽』に行こうぜ『身も心』も(門外漢)
無の中のカタカムナでは 『に』 は『圧力』だが
無の為の裏カタカムナでは 『に』 は『解放』
そうなると 『にんげん』 とは
無の中のカタカムナでは
強い圧力を内側に放出
強い圧力を反対に放出
ふむ・・『心を苦しめる同調圧力』と・・( ..)φメモメモ
無の為の裏カタカムナでは
強い解放を内側に強く放出
強い解放を反対に強く放出
なるほど、『同調圧力(苦)に対する身も心も解放(楽)』か(笑)
人間(認知)が変わる
「に!」っていうのは笑顔でも表現に現れる
笑えばいいと思うよ? 笑の門=rions gate
そりゃ『頭角』を現して『柵を飛び越える山羊』は『圧力から解放』されて『楽な兆しの方へ進む』という『無為自然の摂理』だな


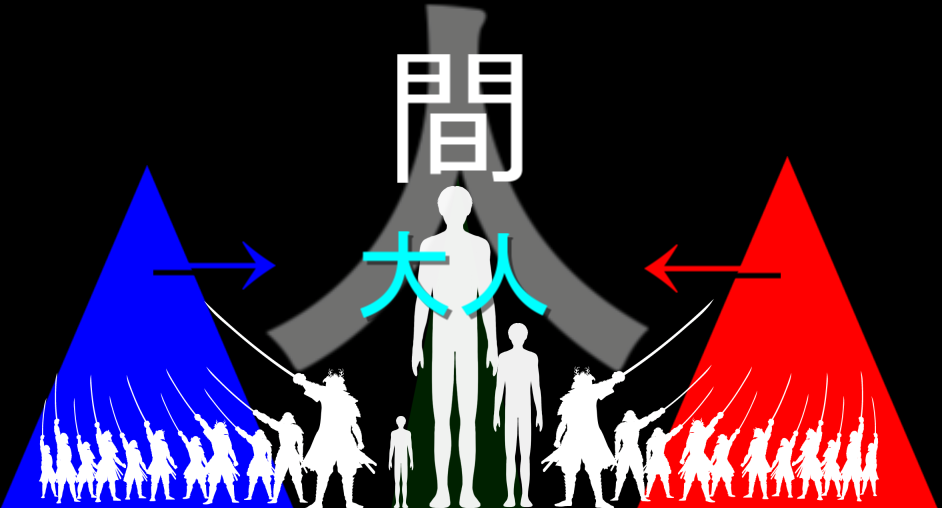

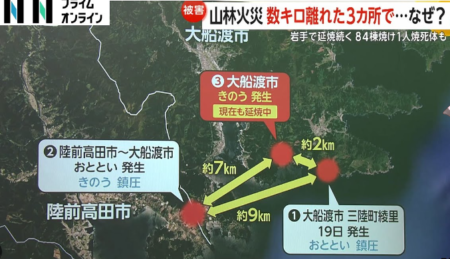


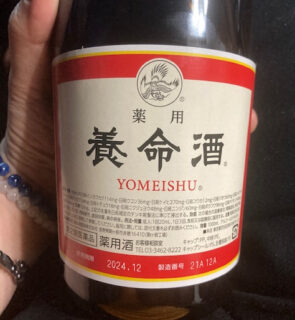

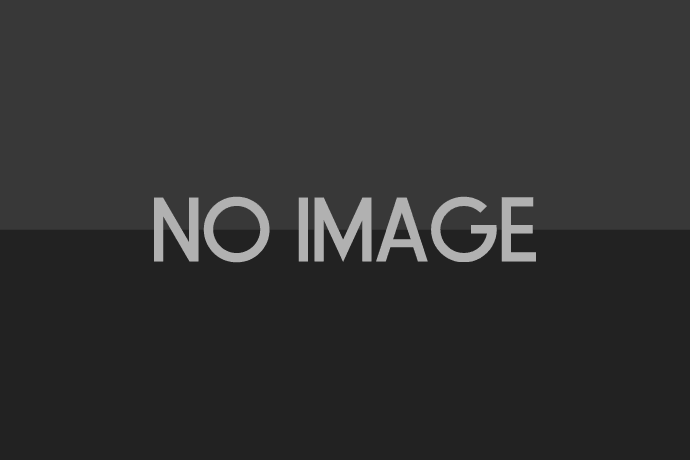



LEAVE A REPLY