現実における客観の一生、夢の中での主観での一生、夢から覚めれば、その一生を一瞬の事と忘却して忘れて・・袖(祖・素)触れ合うも多生の縁があった事を思い出せなくなる=無い袖は振れない=生が無い。まさかこれが真我、一生という共通認知を根底から覆すことわざになるとは・・という気づきのお話
客観的一生と主観的多生
一生とは、この現実における
『生まれてから死ぬまで』という物理的な『肉体を自由に動かせる時限』
「生は一つだから、大切にしなければいけない」という教えの先入観
しかし
『袖触れ合うも多生の縁』
この現実には『生は一つ』ではなく『多く生きる』という捉え方がある
しかし、『袖』ということわざは・・いささか、違う意味を含む
袖の下を渡す
賄賂(わいろ)をこっそりと渡すことを意味します。特に、人目を避けて隠すようにして渡す様子
『袖=お金』という概念に置き換わっている事が
まるで『地獄の沙汰も金次第』と言っているようなもの
たとえ地獄での裁判でも、お金があれば有利になる、つまり、この世ではお金さえあればどんなことでも思い通りになる、という意味のことわざ
無い袖は振れない
お金や財産など、物理的に存在しないものは、どうしようもない状況を表す
どんな事でも『思い通りになる力の象徴の金=袖』が無い
つまり金が無い=生きられない=『生がねぇ』という諦め
まるで、『現実が金剛界』という観点であり、『その中で生きる一生』においては『お金に執着するように誘導』されている
そこで、対比的に逆な行動をしている『袖』を想像すると
『五劫の擦り切れ』という話が浮かぶ
天女が巨大な岩を羽衣でこすり、岩がすり減ってなくなるまでの時間を一劫とし、それが五回繰り返されるほどの長い時間
『研磨』という磨く行為は、硬いもので硬いものを削るから『柔らかいほう』が削られていく
では、この『天女の羽衣』が岩がすり減るまで磨いて削るというのは・・
どれほど『袖がボロボロになるほどの献身』だったのだろうか?
どれほど精神に『初志貫徹の固い意志』があったのだろうか?
まさに『襤褸は着てても心は錦』とは
献身の為に身を犠牲にした『優しき心の結果』が『襤褸』になったという
『汚い世界の意志』に染まって、『凝り固まった人の意志』を磨いて
人として固まった個性を『口封じ』を解き、『人の古い生』を思い出させようと
『袖触れ合う多くの生』に『縁』を与えた事か・・
だから、そんな『縁氣』に触れた人は
『一生』に囚われない『多生という観点』を感じ始める
それが『夢』という『人の口封じ=囚の概念』に囚われない空間
『胎蔵界』での『別の生の体験』である
『体感無くして理解なし』のオリジナルの洞察だが・・
この現実は『死ぬまで一生を確かめる事』はできない
『他人の死』という『物理的に動かなくなる事』を『死と定義』しているだけで『主観的な死の理解』には至らない
つまり『主観的』に「これは死だ!」「死んでない!?」と認知したとしても、それは『客観的』には伝わらない『領域=別空間の話』になる
『終わってみる』までわからない
『続いてるかどうか』もわからない
例え続いていたとしても、『確かめる方法』はない
『戻ってきた』と言ってもそれを『確かめる方法』はない
『死んだ人が見えている』と言っても『見えない』から確かめようがない
『死んだ人と話した』と言っても『聞こえない』から確かめようがない
悪魔=亜空間=阿空観の因果律の証明
『客観』とはそれほど、『曖昧で不確かな嘘=口から虚』と同じなのだ
金剛界では『人の為(客観)』=『偽こそが力』
だから、この世で真実なのは『客観』ではなく『主観』
そして、その主の意志に付き従う体性=『主体性』
他の人が『知識』として知らない、『体験』もしていない
『自分にだけ起きている事』を受け止め向き合う
『人』として『固』まった『集団=集まった口封じの寸の中の個性』
それは『真』ではなく「人とはそういうものだ=サピエンス」と固まった『確執』であり
『角質=死んだ細胞』が覆って、『新しい細胞』が表面にでない
しかし、新しい細胞は『元(古き)』から生まれる『温故知新=温い故に知る新しい』
これは平和・穏やかさの先人達
『争い』が生まれる前の『胎蔵界』
人として口封じされる前の『古き生=祖』と向き合う
『死んだ細胞の積み重なった確執』から離れて『祖と素直』に向き合う
だから私は、これをこう訳す
『祖・素で触れ合うも多生の縁』
『祖』と触れ合う、『元』はなんなのか、『古き生』はどうだったのか?
『素』で触れ合う、『主の糸(意図)』のまま『心に素直に悳』を得る
袖=『神の由緒』 という組み合わせの解釈もできる
『祖は一つ』であって『ひとつではない生様の集合体』
つまり、『祖』こそが『多生』であり、『素』こそが『一生』
なぜこう感じたか?それを説明するのが『夢』という仕組み
『現実』から見て『夢』というのは起きたら『忘れる一瞬の儚い記憶』
その夢の中で感じた『心が亡くなって』至る『今』という『忙しい現実』
『一生を忘却』して生まれ変わっている(輪廻転生)
しかし、明晰な夢の中では、そこに『一つの生』を感じている
それは『一瞬』ではなく『目的』がわからないが『明確な意図』を体験している
つまりは、明晰な夢とは、『一生という生き様』を生きている
ただ、現実に戻ると、現実という人の固まった生=個性というのは
集団(確執・角質)の中では、『表層』に出られず『表現』できない
「人生とは一生である」という口封じの中
その『忘れてしまった一生』は『生では無い』と拒絶する
夢の中で『多生の縁(祖・素)で触れ合った思い出』を『概念・常識で封印』する
『思い』を『出さなく』なって捨ててしまう=『忘却』
私はいつからから、その『多生の縁』に触れるようになり、多生の縁の思い出を大切にするようになって旅日記として『夢日記』をつけ始めた
「こんな面白い体験を忘れてたまるか!」と『忘却に抗う』ようになった
その結果、『思い』を『出せる』ようになった
夢は意味のないもの・・
夢は脳の記憶の整理・・
という現実の概念という『確執や角質』を削り取る作業
『常識』を疑いとっかかりとなる角が立つ『ほころび』をみつけ、削って・・磨いて・・
・・ってこれか『五劫の擦り切れ』やーん!(≧▽≦)と気づいた
自分で自分という『魂(たま)』を磨ききる!という『自己評価、自己認識、自己肯定、自己満足』に至るまで
終わる事はない魂を恣意的に磨く億劫な作業
恣意的とは
自分の感情や思いつき、都合の良いように物事を判断したり、行動したりする様子を表す言葉です。客観的な根拠や理由がなく、自分勝手な考えや行動を指すため、批判的なニュアンスで使われる
これは『客観的な現実』的には『レッテル』だが、『次を支える心の意』と読むと、『主観的精神』では『自己の魂と素直に向き合う事』でもある
それは、現実で『硬い角質(固定概念・常識)』を『弱い布の意志』として削る作業から始まり、襤褸襤褸の『祖・素』をすり減らして『磨いていく生き様』となる
自らで自らを磨く過程で、『多生の縁』とはその『支援』として『素』に『祖の力を和足し』てくれる力
『閃き』であり、『ヒント』であり、『アドバイス』であり、『苦言の戒め』であり、『コツの伝授』であり、『孤高のもの』は『孤高に向かうもの』に『気づいた事を無性で和足したい』
無の心を生きる=『無性』
その為に和足す『無為自然』
実際、私も『気づいた事』を『和足したい』からこそ、同じ方向を目指す存在が現れた時、『祖の一人』になって、素の人の『一生(夢)に現れて伝授』しているだろう
・・という事は、生とは『一生』ではない
『現実』という『物質の肉体の器はひとつ』かもしれないが、『意識・魂・心、カタチを持たない存在』になった時
この現実以外に『別の一生』という『多生』がある
それは時間軸で言えば、『並行』しているとも言えるし、『意識』が『その一生を観測』するまで『止まっているシーン(可能性)のひとつ』とも言える
そのシーンに『祖=体験している』はいて、そこに『素』で入るから『先の祖』が気づいた事を『人と共』養う=『先祖供養』
『夢』で『袖触れ合うも多生の縁』とは
『祖と素で触れ合う別の一生』と感じる
今年のライオンズゲートの体験をまとめてみると、遊び、遊ばれ、楽しく学んだ『多生の縁』だったと思うと同時に
やはりこの現実は、『和』の無い『金剛界』なのだと実感する
『否定や拒絶』をするには、それが『何』なのか『見極め』ないといけない
渡してはいけない、『和』として足したら『差』が生まれてしまう物事もある
取引・駆け引き(×-)という悪(÷)巧み
それを和(+)足してはいけない『継承してはいけない』と
『警鐘の形象』を夢で渡される
それは、現実(周り)に対して警鐘する事ではなく、『自己の心の内面』に潜ませてはいけないという事
『潜在意識』に植え付けられた『間違った概念』と向き合い
『先在意識(祖)』と共に素(心)直に正していく作業
それが、『自己探求』であり、『自己治癒』である
その『夢の入り口』に立つ事が『莫迦の一つ覚え』
門の前に人が立つ=『閃』
漠然として広大な『なんでもありの夢の中』を漠然と迦(巡り合う)
そして『目的』のための『明晰な夢を意識して観測』して『達成』する
達成するという事は『出口』を見つける事
入口を見つけて、出口を見つけたらもう莫迦の『一つ覚え』ではない
体験を持ち帰り、経典としてまとめる『自己表現の弥勒』となる
そんな『現実の客観』からみれば、数時間から一晩『意識を失っただけ』
しかし、『現実から離れた主観』では、そこに『生まれて(役目の入口)』から『死ぬ(達成)まで(出口)』の『一生』があった
『一生の役目』を終えて現実に『生まれ変わった』
その現実から見て『過去生』を忘れてしまえば・・
『現実での一生』を繰り返す事になる
『祖・素』でを『袖=お金』にすり替えた『生が無い亡者の世界』で
『人』という『固』まりの集団、『一塊』の空間
硬い石の確執と角質(固定概念・常識・死んだ細胞)
『囚われない意識』は『観測対象を自由に向ける事』ができる
自由に『観たいものを観るという意志』が生まれた時
『この世界が否定・拒絶している禁忌』に『観測の目が向く』のは一番最後
『目先の欲に目が眩む』事なく、その『眩ませる(欺き・騙す)』の向こう側
そこに『何』があるのか?
現実も『可能性の一生のひとつ』でしかないが、『可能性の一生=夢と同じ』ならば、『入口』から入ったという事は必ず『出口(目的達成)』がある
それを人は、『宿業』と呼ぶが・・『人は生まれてきた理由』を『忘れて』いる
まるで『夢から覚めた直後』のように漠然とした『なんでもありの現実』
『間違いの空間』に囚われる=ヤコブの夢
この瞬間・空間が夢か現実かも『夢現』がわからないから、生きてるか?死んでるか?も実はわからない
だから、『夢日記』という『一意識の位置座標』を記録する事で
『多生の縁の中の一つ』であると認知すると
「ではこの一生では何が目的だったかな?」と
『頭空っぽ(sponge)』にして『夢』詰め込める=チャラしてへっちゃら
『祖と素』で触れ合う、『謎解き冒険ゲームの遊び』が始まる
そして、『襤褸』は着てても心は錦の『天女の献身』という『縁氣の支え』があると気づき
言葉を『慎む事場』
心の真を捉える事の場
それは心の芯=『自然』を『支える心』
自然とは・・『目に見える物理的な環境』に限らない
『目に見えない領域』を漠然と巡る『エネルギーの流れの一部』に成る事
『心に素直な存在』こそ『祖の意志に気づく役目』である
最も簡単で、最も難しい・・中心を保つという『苦行』に見えて
『今』を『主観』で『夢中で楽しむ遊び』でもある
そこには『自他』はなく『自己』しかない=真我以外一切無常
真が「生まれたい」・・望めば『我』が生まれる
我が「欲しい」・・と望めば『欲望』が生まれる
欲望にのめりこむと我を『忘れる』
我を忘れると、何が目的だったか『忘却』する
忘れた事を思い出そうとすると、『夢』が生まれ
夢の中で、祖・素で触れ合う『多生の縁の体験』をして
心に素直になると、『事場を慎む真言』を思い出し
『言葉を事場』に言うを止めれば、『真』に至る
言う=『我』を欲する
「我思う、故に我有り」
『口』から『虚ろ』が飛び出し『空』を彷徨う=虚空
『有る無し』の『虚空』が『事場の人を口封じ』=『囚人の集団』を生む
口は禍の元(笑)
だが・・黙っちゃいられないのが、『自己表現の弥勒』となった
現実では『死人に口なし』の先人達は、『気づいた事を口』にする
それを夢を通して先の祖を人と共に養う心に素直な先祖供養をする『現実の人』に
『虚空』を語り伝え、現実の外を『和足す』のである




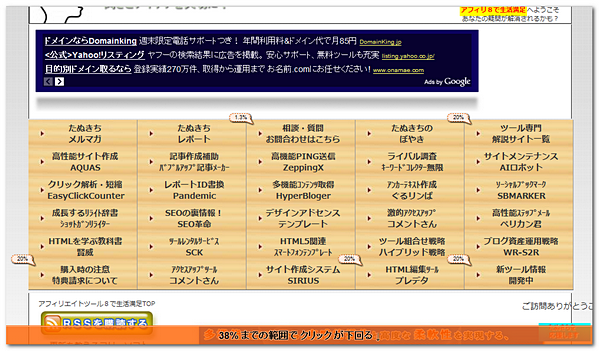
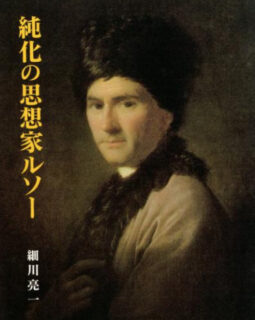
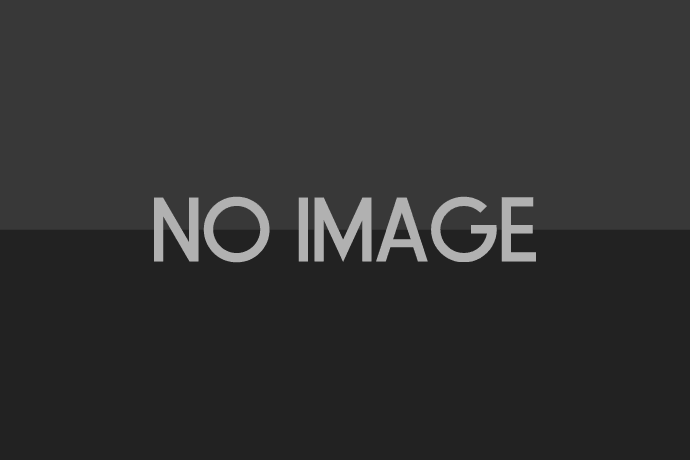
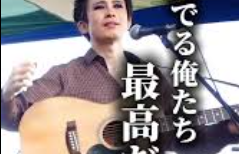
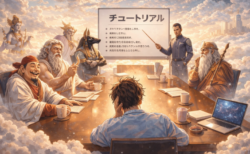
LEAVE A REPLY