寝起き閃ワード 経訓…訓読みと音読み、私の漢字解釈が観世音の感覚と素直に形分解読みをしてたが、神仏一体(漢字)を分離して捉えていた経訓読みと神音読みと気づいたら、え?これ…法華経訓読だった!という気づき
教訓とは
おしえさとすこと。またその言葉。
ま、これが一般的で、主に『失敗して物事を身に染みて理解』した時に、『戒めの言葉』として「いい教訓になったな」と気を引き締め、「その過ちを繰り返すなよ!」と『後世に伝え残す項目』
なのだけど…
それは『未経験』の奴が、『教科書通りにただ言葉を教える』のでは
…違くね?
『体験』ありきの『しくじり先生』だからこそ、その『過程にある詳細を伝承』できる訳で…
と『教』の部分に『違和感』を感じたので、今日は経典の方から『経訓』という言葉を思いついた
『訓読み』のいい所は、『ひとつで理解』できる事
あるいは『送り仮名』を持って理解に至る事
とりあえず、適当に 『山』 で言えば
訓読みは やま
音読みは さん
さて、ここにも実は面白い発見をした
ヤマ・ニヤマ→『戒律・法則』
さん → 『三千世界 SUN 太陽』
やはり『経典』から来ている…と感じた時
そもそも…『経訓』って言葉はあるのか?造語なのか?を調べたら…驚きのシンクロニシティ!Σ(゚д゚;)
法華経訓読?!
経訓
経書の訓詁(くんこ)。経書の解釈。〔後漢書‐鄭康成伝論〕
訓詁
《「訓」は解釈、「詁」は古語の意》古い言葉の字句の意義を解釈すること。「訓詁注釈」
中国古代の聖賢の教えを述べた書物。儒教の経典。四書・五経・十三経の類。経籍。
法華経訓読…という言葉が出てきた事
かつての夢を通して、私は『古代律令制の三省』に関わる過去世の縁があったのか、難しい言葉が妙に引っかかった
『妙法蓮華経』はこうやって『縁ある者』が出逢うのだね(´-`)oO
『訓詁』が特に私の中で刺さる表現
『古語を解釈する』という『温故知新』
『故事成語』は事故と成った語りの『経訓』
ほら、つまり
『体感(実践)が先』で『理解(知識)は後から』着いてくると、日々の自分が『口』に出していた『真言』
『訓詁を知らず』とも『古語を解釈する』という『門前の小僧は習わぬ経を読んでいた』のだ
そんな『門外漢』が『経訓』を『独自解釈の妙法蓮華経』で読み解くとこうなる
糸又土言川
(主の)糸は又土に
言うは川の流れに
これは『自然の摂理』と『人の愚かさ』を端的に捉え達観した景色が見える
まるで「この世は思い通りにはならない」という涅槃寂静の『生病老死』にも通じる事で
『砂に書いたラブレター』と表現しよか
『伝えたい想い』があるから『主』は『意図』を遺す
しかし、それは『実践無くして理解できるもの』ではなく、理解する頃には
糸は又土に、言うは川の流れに…
砂に書いたラブレターは『消える前しか読めない』ように
「なんか…あそこに文字書いてたで?」
知らんけど┓(^ワ^)┏ ← ただ教える訓
『中身が無い言葉だけ教える教育』では
『古語』は知っても『故事成語』はわからない
なぜそのラブレターを『砂に書いた』のか?
その『行動の意図』までは伝わらない
『妙な方法』を『泥のつかない清い水(蓮華)』のような『素直な心で正直にやった奴』しか理解出来ない
「アーナンダ!僧言う事か!」
『阿難』という釈迦の話を最も多く聞いた弟子
『多聞第一』…でもこれ解釈を
『たもん』と詠むか、『たぶん』と読むかで『重さも解釈』も『存在意義』すら変わって来る
たぶんと呼べば『曖昧な多分』になる
『真言の教えを護る』となると『多聞天』(密教の守護鬼)
阿難無き世界
アヌンナキの世界は『二つ』産まれる訳だ
『真言(自分)』を護るか
『偽=人の為』とするか=多分
これもまた『一切』を捨て『孤高の上』を目指す『初期仏教』と
それ以外の全ての者=『釈迦の邪魔をしそうな思想の陽動』と考えれば…
『孤高、真言、蓮華の心』を持つ者は、『釈迦の教え』なき『廃仏毀釈の世の中』に『違和感』を感じ・・『妙な光』…『妙な音』…に勘づいて、それを『探求する事が全て』になっていく
気がつけば『妙』は『明』へと変わり『明光、明音』と感じている感覚が『明らか』になっていく
『教えられている事』に共鳴せず、『禁忌や禁止』と呼ばれてレッテルで隠されている所に『妙な気配』を感じるからこそ
『門下生』ではなく、『門前の小僧(漢字)』でしか『習わぬ経訓は詠めない』のである
ここが『南無阿弥陀仏』と『南無妙法蓮華経』の違いを独自感覚で
お釈迦様=物が『おしゃか(壊れる)の様』になる
阿弥陀仏は、『紛争が全て崩れた仏』→『自然に還る』
『廃仏毀釈』で一旦、『正法は無』に還る
南無妙法蓮華は
『妙な方法』の『正直な清い水の心』
自然に還った仏の『糸は又土』に『言う川の流れ』に『妙な見方をする水の心』は見つけてしまう
「川…淀でね?汚くね?」(´・ω・`)Σ(゚д゚;)
『言葉の流れ』がおかしい、正しくない・・『源流』の『上から流れてくる教えの言葉』の解釈が『変な混ぜ物』が入ってるぞ?と
『教』という文字の組み合わせは
『土の子』を『仏陀切り(袈裟斬り)』に『鞭で叩く』
という組み合わせなんだよね
これ…また面白いのが
仏陀切る→袈裟斬り→衣(けさ)の上に加沙→シャカ(サカ)が出てくる
『サカ(釈迦)族を根絶やし』にする『廃仏毀釈』を一言で書いてる
『経訓』が『教訓』になるだけで、『経典を貶める言葉の呪術』の完成
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い!」
当然、その『訓詁』まで『書き換えられる』だろう
「お前らの教えなど、こーして、あーして、敵を増やしてやろう」
多分、どっかの時代で『こうやつ』がいたら、『その後の教訓』は『全て間違い』の方向に行くから、『ペンは剣よりも強し』
その『紙様』を『神様』として『偶像して崇拝する力』が生まれる
『教科書(聖書)』は絶対!ってか?
『言う川の流れ』が汚れ、淀み、そのうち『停滞して腐る』から、『腐った言葉』が生まれ、それを『流行り』で意図的に停滞を流そうとして『死語』が増え、いよいよ『流れが止まる』と
「もう言葉いらなくね?」と『言語を放棄』する
問答無用の言語道断が起きる=言論弾圧、世論操作
「この言葉は使ってはいけません、禁忌です」
さて、『現代故事成語』のお勉強です
『コロナ禍』に『専門家と名乗る者達』が『教訓』として『何も理解してないのに教えた方法』は『全て間違って』いて
その「全てが間違っている!!」と『魂の声』を上げていた『心に正直に正しい声を上げていた人達』から『先に世を去りました』
これが『経訓』であり『訓詁』です
言川言古
言うのは『かつての流れ』
言うのは『古い話』
『今は昔』の話だが
『今も昔』と同じ今昔物語
それが『経典の訓詁』の訓読み
『門外』に伝わりし『漢字の生活(実践)の知恵』から生まれる『先世見の読解力』
またこの『読む』という漢字も
『詠む』を貶める構成
言うを『売る』
言うを『永く』
まさに『目先の欲の号外』
『語り継ぐ』を『切り取る』
…こうやって…『妙な見方』をするのは『心に正直』に『与えられた意味や解釈』を聞いた時、『音の響き』と『心の振動』が『共鳴』してないんですよね
『納悳』出来ない
『鵜呑み』に出来ない
噛み砕いて『神』砕いて
咀嚼して『祖借』しなければ
呑み込めない!…
神=『示申』
砕=意志の『九十(事・苦渋)』
祖借=祖を借りる、『祖の人の昔』
本当に『神』か?と『心が示し申す』
偽=『人の為』の『真偽を問う』ために
『祖の人昔の知恵』を借りる
『判断』に困ったら『分解』する
分解して『訓詁を元』に『今昔』を問う
「昔から『この味』だったか?」
これを覚えているのは『祖先』である
『血』となり『肉』となり、『自然の共存細菌』として、『免疫力』として、『生きる生活の知恵そのものの経典』になった
『かつての形』が『壊れたお釈迦様』、阿弥陀仏で『崩れて仏』となり、糸は又土に還り言う川の水となって、『経訓を継承』した『自己解釈をする助け』になる
そうか、だから『明鏡止水の観世音』なのか!
『水のように清い心』に落ち着く
これが『蓮華』
その『水』が形が無くなった『宿した先祖が生きてる』という事か
あ、言葉が閃いた
神苦仏陀
神は『苦しみ』を与え
仏は『崩壊』する
…って良い意味ないじゃん!
と思うでしょ?(ヾノ・∀・` )Σ(゚д゚;)
神=示し申す→『心』
苦しい…というのは感情では無く『体感』
喜怒哀楽ではなく、それに『伴う全て』
喜びで『胸がはち切れそう』で…苦しい
怒りで『頭が割れそう』で…苦しい
哀しみで『胸が締め付けられ』…苦しい
楽しくて『腹がよじれて』…苦しい
この苦しいという『感覚』は『心が身体』に与えている
それによって『生を活きている生活の実感』を得る
一方で『仏→忌→己の心』
『自己』という関係性に置いて
『自』が『大いなる親の心』ならば
『己』はそこから産まれた『子の心』
子は色んな事に『意欲と好奇心』を抱き「なんでも体験してみたい!」と『感動』を求める
ここでさっきの『喜怒哀楽体験』を『忌=エゴ』として『満たされ過ぎて苦しさを伴う』から、「もう必要ない」と思ったら『禁忌=とどめる己の心』にする
これは例えるなら
子供の頃は『痛み』の度に『泣いていた』
泣けば『周りが反応』してくれるから
大人になれば『痛み』で泣いた所で、周りは『さらに弱みに漬け込んで来る』から泣く事は無くなると『泣くを禁忌』にするように
体験をさせる『自=示申→神』
体験を持って『禁忌とする自分→仏』
『体感』無くして『理解』なし
『理解』したら『禁忌の経訓』として『古語』になり
それは『訓詁』として…
書いた所で『伝わらない』(思い通りにならない)
砂に書いたラブレター(笑)
この『崩壊、形』が無くなる
そこに『こだわり=執着』が無くなる
すると、ここだけに書いた『経訓』は、『自然』を巡って『それを求める者に寄生』する。「ただいま!」と『居心地がいい息=自心が苦しくない理想』へと帰省する
『神』砕いて=『示し申す心』の意志の『苦渋』
苦渋を舐める=『辛い体験』をする
この苦渋もまた『妙な捉え方』をすれば『前向きな形』に見えてくる
草古氵止めて中心へ/から
自然の古い山水止め中へ
『水の湧き出る穴』は『水の流れ』が止まらないと、その『出処を辿る事』は出来ない
水から止める意志=『根源・ルーツ』
自ら止める意志=『禁忌と向き合う』
苦渋を舐める?
「苦渋をなめる」は誤用であり、正しい表現は「苦汁をなめる」です。これは、つらい経験や悔しさ、屈辱などを繰り返し味わうことを意味し、新人時代の失敗や不遇な状況など、非常に苦しい経験をした際によく使われる表現です
ははは(≧∇≦)莫迦が引っかかとる
舐める=『舌』に引っ張られて『味』に寄せて『汁』にしてどうする、それが『教訓』の間違いなんだよ
舐めるなよwww?
なめんじゃねーよ!
『苦渋』はあえて『嘗(な)める』のだよ!
嘗とは味わう、試す、こころみる、経験する
ね?これが法華経なんよ
(方法の教科書では無く生活の知恵)
見切り発車で、取り合えず『訓詁』として伝わってる言葉の『漢字のままに分解』して読んで見ると
『苦渋の意味』がちゃんと『詠める』
正しく読めない者が「舐める…だし、舌なんだから味関連で、きっと汁の方がいいだろう!」と置き換えると
『止めるという意志』が無くなる
山水十=山の水が全て→垂れ流し
流れの元の穴を辿る為の『嘗める』も消える
『試みて経験する(失敗も含めて)』が無くなる
ちゃんと詠め(´・ω・`)言う永く
『舐めてる』から『目先の号外』ばかり『読む』→言って売る
『売る為』なら『何でもするのが商売』だから『事件の捏造』?そんなものは『人の為=偽のお家芸』
法華経の実践者、門外漢を詠む
門前の小僧=『心に素直に神仏宿す者』は、『経訓詁』としてこれを覚えとけば、『目先の欲』に流されず『禁忌』できる
神苦仏陀
神(示し申す)は苦しみ=『自然の古き』を与え
仏は形ある者が滅び去り『循環する』自然へ導く
『今は昔』へ還り、『今が昔』となって繰り返す
先祖は『子孫の過去』となり、子孫は『先祖の未来』となる
『人の形』は『後』から着いてくる
それが体感無くして理解なし
砂に書いたラブレター
思い通りには伝わらないもんさ
音読みの説明忘れてたなw
音読みは神の恩詠み
山→さん→太陽
海→かい→ Χ(かい)、キリストを象徴
さてさて、これは『宗教の匂い』がする…けど、教=土の子を『仏陀切って鞭で叩くがある』という事は…
元は『経典(実践)』だったはずなので
太陽神の子=統治者・導く者→『キリスト』
という意味では、山(太陽)から湧き出た水(海)
『山から湧き出た山水』ならば、それは『自然の生命の恩恵』として不思議な景色が見えるけど『恩』で繋がっている
『太陽の熱』が『氷』を溶かして『海が産まれた』としたら?地球という環境においては、『かつては凍らされていた』という『地球氷河期仮説(誰も見てない)』がある
そうなると、キリストは『母なる海からやってきた』という、『母親の謎がひとつ巡る経路』に見えてくる
仮に、聖母の呼ばれる『処女懐妊』も、目に見えない『細菌感染』という形で『寄生して宿った』とするなら…『スピーシーズ(スターシード)』とも言えるが
それは『恩』じゃなくて・・『因を支える心=寄生されちゃった後』の祭り・・あまりにも『エイリアン宗教寄り』になるので、なんか(´-`)oOつまんね Σ(゚д゚;)
だから私は『山(やま)と海(うみ)』
この『訓詁詠み』の方が波動的に落ち着きます
ヤマは『戒律』、つまりは「かつてそんな事があったから戒めよ」という『訓戒』
海は生みの親、生む、『無から有を生み出す』と同時に、『経訓』として、『土に還り、川の流れ』で至った『先祖達が還った場所』でもある
その『かつての生き様を持った水の流れ』が、『太陽熱で気化』して『自然の様々な細菌』と共に、『陸で生きる人に風として吹き抜け浸透』して
「気に入った奴には寄生しよう」として『風邪』になり、『免疫』として正体は『先祖が旅の宿を求めて来てた』ようなもので
「一宿一飯の恩義として、免疫になる知恵を授ける(ヾノ・∀・` )(≧∇≦)勉強」
こんな感じだから
ある時、突然、どこ吹く風のように『気の向くままに現れた先祖』がこんな小ネタを投下していく
訓読みと音読みは
『神』恩読みと
『仏』経訓詠みと
『妙法蓮華』で詠んでみな?
その心は?(´・ω・`)
Come on(」゚Д゚)」oh my God
観音(」゚Д゚)」お前神
神は『生き様』を与え
仏は『死に様』を観る
それは内に宿した『一体の経訓』
どうせ『仏の真理』を伝えた所で生きる間は『神の領域』
『死に際』に遺した『置き手紙の言伝』は
『風化』していく砂に書いたラブレター






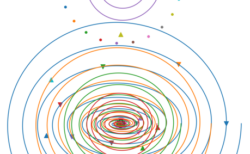
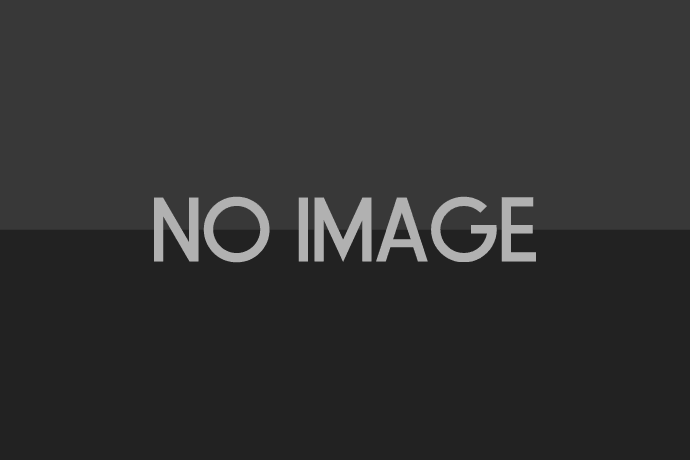
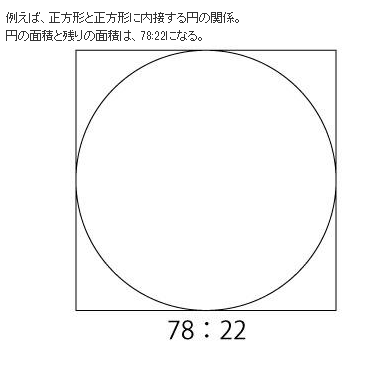
LEAVE A REPLY